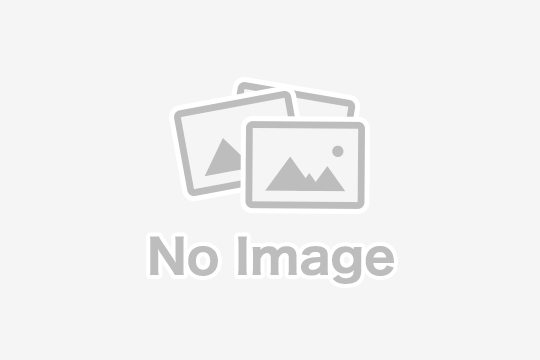行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。
経歴:開業以来19年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
行政書士のプロフィールはこちら
人が亡くなれば、その亡くなった人の残した銀行預貯金や、
保険金、株式、不動産、自動車などの財産を、
相続人が相続することになります。
ただ、相続するためには、そのための手続きが必要になり、
特に、戸籍については、どの手続きにも必ず必要とされるものなのです。
では、相続に必要な戸籍とは、どんな戸籍があると思いますか?
亡くなった人の銀行預貯金の相続でも、保険金や株の相続でも、
不動産の相続でも、どの相続でも共通して必要になる戸籍が、
被相続人(亡くなった人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍です。
しかし、生れてから亡くなるまでの戸籍というのは、
単純に、戸籍を1つ取得すれば良いというわけではありません。
なぜなら、人の生まれてから亡くなるまでの戸籍というのは、
除籍謄本(じょせきとうほん)、原戸籍(はらこせき)、
戸籍謄本(こせきとうほん)という3種類の戸籍があるからです。
では、被相続人の戸籍として、その3通分の戸籍があれば良いのでしょうか?
いいえ、戸籍の種類としましては、3種類ですが、
これは最低でも、3通分は必要ということです。
なぜなら、除籍謄本と原戸籍については、
婚姻、離婚、転籍、年齢などによって、
人によって、その存在している数が違ってくるからです。
ある人は、除籍謄本と原戸籍が合計5通の人もいれば、
再婚歴や転籍歴のある人、または、高齢の人なら、
除籍謄本と原戸籍が、合計10通前後の人もいらっしゃいます。
では、相続に必要な戸籍として、他にどんな戸籍が必要と思いますか?
上記でご説明しましたように、
被相続人(亡くなった人)の生れてから亡くなるまでのすべての戸籍、
つまり、除籍謄本、原戸籍、戸籍謄本それぞれ何通か必要になります。
ただ、相続に必要な戸籍としましては、それだけでは足りません。
なぜなら、相続人全員の戸籍も必要になるからです。
では、相続人全員の戸籍があれば、大丈夫と思いますか?
たしかに、相続人が子供さんの場合には、基本的に大丈夫です。
そしてもし、被相続人(亡くなった人)に養子がいれば、
養子も子供ですので、
養子の人の戸籍も必要になります。
しかし、相続人が、被相続人のご兄弟姉妹、
甥姪の場合には、まだ足りません。
なぜなら、相続人が、被相続人のご兄弟姉妹、甥姪の場合には、
被相続人の父親と母親の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍も、
必要になるからです。
ここで重要なのが、父親も、母親も、
両方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍が必要になるという点です。
つまり、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍と同じように、
被相続人(亡くなった人)の両親についても、必要になりますので、
その部分だけ単純に考えても、3人分(3倍)の量の戸籍が必要になるわけです。
ではなぜ、それらの戸籍も必要になると思いますか?
それは、被相続人(亡くなった人)の残した預貯金や保険金、株や不動産などを、
相続する手続き先で、必要書類として決められているからです。
そして、被相続人の兄弟姉妹が、戸籍上、
誰々なのかを特定するためで、
相続人を特定するためでもあるのです。
相続の手続き先では、どこの手続き先でも、
所定の手続き書類に、相続人全員の署名と押印が必要になります。
その時、相続人全員という点が重要で、
相続人が1人でも抜かっていると、書類審査にひっかかり、
いつまでも相続手続きを済ませることができない状態になるのです。
そうならないためには、抜かりの無い相続に必要な戸籍類と、
それらの戸籍類から導き出された相続人全員の署名と押印が必要になるのです。