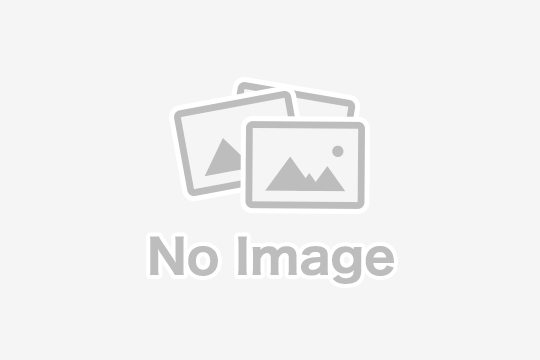行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。
経歴:開業以来19年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
行政書士のプロフィールはこちら
戸籍謄本も除籍謄本も原戸籍も、
その戸籍の本籍のある役所でしか、
取得することができません。
ただ、その戸籍の本籍のある役所が近ければ良いのですが、
遠い時には、役所の窓口まで行くことが難しかったり、
交通費がかなりかかったりするものです。
そのような時には、無理に役所の窓口まで行かなくても、
役所に戸籍の請求書類を郵送することによって、
戸籍の謄本類を取り寄せすることができます。
また、戸籍の本籍がどのくらい遠いかなどは関係なく、
たとえ、すぐ近くに戸籍の本籍のある役所があったとしても、
制限なく、役所に戸籍の請求書類を郵送することができます。
つまり、戸籍の本籍が遠い時だけでなく、
役所の窓口の人とのやり取りが苦手な方にとっては、
多少準備に手間はかかりますが、
郵送で戸籍の謄本類を取り寄せるという選択肢もあるということです。
もちろん、仕事やその他の事情で忙しくて、
なかなか役所の窓口まで行けないという時にも、
郵送で戸籍の謄本類を取り寄せるということもできる訳です。
もちろん、郵送で戸籍の請求書類を送る時には、
役所の窓口で戸籍の謄本類を取得する時と同じ書類が必要なのですが、
それ以外にも、返送先の住所が記入された返信用封筒が必要になります。
ただ、役所から戸籍の謄本類の返送先の住所については、
どこの住所でも良いという訳ではなく、
戸籍の謄本類を請求する人の身分証明書の住所と、
同じ住所でなければなりません。
具体的には、戸籍の謄本類の請求用紙に住所と氏名を記入するのですが、
その住所と、運転免許証などの身分証明書の住所と、
戸籍の謄本類の返送先の住所は、
すべて一致していなければならないということです。
もし、一致していない住所を返信用の封筒に記入していたとしても、
その住所宛てには、役所からは送付してもらえませんので、
注意が必要です。
また、返信用封筒については、封筒の大きさなどの指定はありませんので、
どんな封筒でも良いのですが、
あまりにも小さい封筒の場合、戸籍の謄本類が入らないということもあります。
そのため、通常は、どんなに小さくても、
定形の長形3号(A4サイズ横3つ折り)の封筒か、
できれば、戸籍の謄本類を折らなくても入る角形A4サイズの封筒が良いでしょう。
戸籍の謄本類を折ってはいけないということは無いですが、
もし、その謄本類を使い回しする場合には、
最初はきれいな状態で手に入れておいたほうが、痛みにくいからです。
また、どの大きさの返信用封筒であっても、
返送に足りる料金分の切手を貼っておく必要があります。
つまり、役所の担当者が、返送書類の重さを測って、
切手を貼ってくれるというわけではありませんので、
自分で、不足の無い程度の料金分の切手を貼らなければならないということです。
なお、急いでいる時には、返信用封筒の表面の一番上に、
赤で速達と記入して、速達料金分の切手を貼っておくと、
役所の担当者から、できるだけ急いで返送してもらえるでしょう。