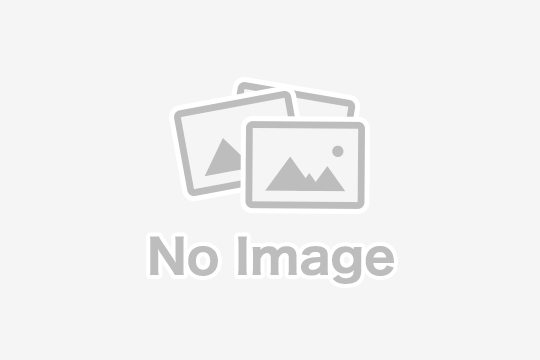行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。
経歴:開業以来19年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
行政書士のプロフィールはこちら
原戸籍(げんこせき、又は、はらこせき)というのは、
正式名称は改製原戸籍(かいせいげんこせき)と呼ばれるもので、
戸籍謄本、除籍謄本(じょせきとうほん)と並んで、戸籍の一種です。
この改製原戸籍は、主に、相続の時に、
亡くなった人の戸籍類として、戸籍謄本や除籍謄本と同じく、
必ず必要になる戸籍となっています。
では、戸籍謄本と原戸籍とでは、どんな違いがあると思いますか?
まず、大きな違いとしましては、2点あります。
1点目の大きな違いは、戸籍謄本は、現在の戸籍であって、
原戸籍は、過去の戸籍という点です。
たとえば、同じ人の戸籍であっても、
その人の現在の戸籍が戸籍謄本と呼ばれるもので、その人の過去の戸籍が、
改製原戸籍(かいせいげんこせき)と呼ばれるものなのです。
ただ、ここで注意が必要なのが、
改製原戸籍は、1つではないという点です。
年齢の高い人ほど、その人の改製原戸籍は、2つ、3つ・・・と多く存在しています。
ではなぜ、年齢の高い人ほど、
その人の改製原戸籍の数は多くなると思いますか?
それは、改製原戸籍の作られ方に、原因があるのです。
改製原戸籍が作られる時というのは、法の改正によって、
新しい様式に戸籍が移し替えられる時となります。
その時に、古い様式の戸籍と、新しい様式の戸籍ができ、
古い様式の方の戸籍が、改製原戸籍として、
以後、その役所で保管されることになっているのです。
つまり、法の改正によって、戸籍の様式等に変更があるたびに、
戸籍が移し替えられることになりますので、
改製原戸籍も、その数だけ作られていることになるわけです。
では、具体的に改製原戸籍は、いくつあると思いますか?
過去、法改正のために、改製原戸籍が作られたのは、
少なくとも、平成に入って1度、昭和の時代に2度、
大正の時代に1度、明治時代に2度ありました。
そのため、たとえば、昭和の初めごろに生まれた人でしたら、
改製原戸籍が、少なくとも3通はあるということになります。
大正生まれの人なら、少なくとも4通はあり、
明治生まれの人なら、5,6通はあることになります。
ただ、人によっては、昭和生まれの人であっても、
改製原戸籍が、5通も6通もある人もいるのです。
ではなぜ、昭和生まれの人なのに、
改製原戸籍が5通も6通・・・もあると思いますか?
実は、法改正がされても、戸籍の移し替えを実施する時期というのは、
役所によって違っているからです。
具体的には、ある役所では、法改正がされた後、
すぐに、戸籍の移し替えを実施して、原戸籍と、戸籍謄本ができるのですが、
別の役所では、法改正によって、数年後に、戸籍の移し替えを実施して、
原戸籍と、戸籍謄本ができるといったことになります。
そのため、もし、ある役所で、戸籍の移し替えが実施され、
原戸籍と戸籍謄本ができた後で、婚姻や離婚、
本籍移動のために別の役所に転籍した場合、
その役所でも、戸籍の移し替えが実施されるということがあるからです。
その結果、たとえば、平成の法改正は1度なのですが、
平成の法改正による改製原戸籍が、2通や3通もある、という人も、
婚姻や離婚、転籍のタイミングによってはいる、ということになります。
昭和の法改正による改製原戸籍についても同じで、
婚姻や離婚、転籍のタイミングによっては、昭和生まれの人でも、
その人の改製原戸籍は、5通も6通・・・もある人がいることになるのです。
そういったことから、相続で、亡くなった人の原戸籍を取得していく場合には、
少なくとも法改正分の数の原戸籍が存在していることと、
婚姻や離婚、転籍などのタイミングによっては、
さらに多くの原戸籍が存在している可能性があることを認識しておくと良いでしょう。
なお、相続では、亡くなった人のすべての原戸籍だけでなく、
戸籍謄本や除籍謄本も必要になります。