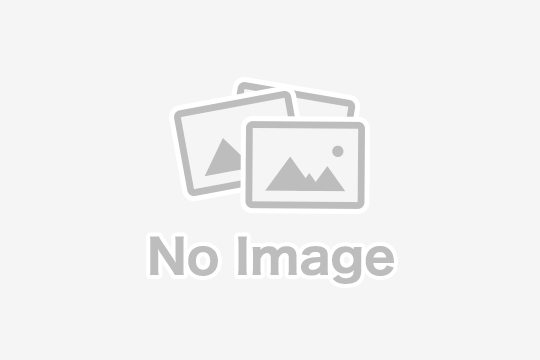行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。
経歴:開業以来19年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
行政書士のプロフィールはこちら
相続戸籍とは、ある人が亡くなった時に、
亡くなった人の相続の手続きで必要になる戸籍のことを言います。
つまり、相続戸籍とは、相続に必要な戸籍とも言えるのです。
ただ、戸籍と言いましても、
相続の戸籍では、戸籍謄本だけのことを言うのではありません。
相続戸籍では、改製原戸籍(かいせいはらこせき)、除籍謄本(じょせきとうほん)、
戸籍の附票(ふひょう)といった戸籍類も含まれますので、
それぞれの意味と、違いを理解しておく必要があります。
戸籍謄本については、まだ、ある程度どんなものなのか想像できる人や、
見たこと、取得したことのある人も多いかもしれませんが、
改製原戸籍や、除籍謄本については、初めて知る人が多いかもしれません。
まず、改製原戸籍や除籍謄本の意味は、
改製原戸籍は、法改正によって新しく作り替えられる前の戸籍という意味で、
除籍謄本は、その戸籍内の人が全員いなくなった戸籍という意味です。
いずれも、戸籍謄本と同じく、
戸籍であることに違いはありませんが、改製原戸籍も除籍謄本も、
簡単に言えば、前の戸籍、つまり、過去の戸籍と言えます。
逆に、戸籍謄本は、今の戸籍、つまり、現在の戸籍と言えるのです。
次に、相続戸籍の具体的な例としましては、
まず、被相続人(亡くなった人)の出生から亡くなるまでの戸籍となりますが、
あくまで、それは最低限必要な戸籍となります。
被相続人(亡くなった人)の戸籍というのは、
その人が、何もしてなくても自動的に増えてきた改製原戸籍と、
その人が、転籍などの届け出によって増えてきた除籍謄本が多々あります。
つまり、被相続人(亡くなった人)が、たとえ一生独身であったとしても、
法改正の結果によって自動的に増えてきた改製原戸籍と、
その戸籍内の人が全員いなくなることによってできる除籍謄本が存在するのです。
たとえば、被相続人が亡くなった時の戸籍内に、
被相続人以外に誰もいなかった場合、
その戸籍は、被相続人が亡くなった時点で除籍となります。
その除籍を役所から発行してもらう時には、
戸籍謄本ではなく、除籍謄本になるわけです。
少しわかりにくいかもしれませんが、その戸籍の名称も「除籍」に変わり、
実際に、誰もいなくなった戸籍には、「除籍」という印が戸籍に押され、
それを役所が発行する時にも、除籍謄本という印字がされて発行されます。
改製原戸籍についても、理由は法改正によるものですが、
新しく作り替えられる前の戸籍には、「改製原戸籍」という印が押され、
それを役所が発行する時にも、
改製原戸籍 または、原戸籍という印字がされます。
なお、改製原戸籍(かいせいはらこせき)については、
読み方も若干むつかしいですので、
省略して、原戸籍(はらこせき)と呼ぶことの方が多いです。
役所の人や、戸籍を専門に扱っている人の間では、
原戸籍(はらこせき)を、さらに略して、
(はらこ)と呼んでいる人もいます。
まとめますと、被相続人の遺産を相続するためには、
以上のように、戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本の3種類の相続戸籍が、
かならず必要なのです。
ただ、相続戸籍の種類は3種類なのですが、
3通という意味ではなく、たとえば、改製原戸籍が4通、除籍謄本が5通、
戸籍謄本が1通といった人も多く、
ある亡くなった人の相続戸籍は、3種類で合計10通といった感じになります。
また、相続戸籍が、被相続人の遺産の相続必要な主な理由は、
被相続人の相続人が誰々なのかを、
第三者に証明することと言えます。
ここで言う第三者とは、被相続人の遺産を預けている銀行などの金融機関、
不動産を管轄している法務局、
証券などを預けている証券会社などのことです。
つまり、相続戸籍とは、亡くなった人の遺産の相続手続き先に、
被相続人の相続人を証明するために必要ということになります。